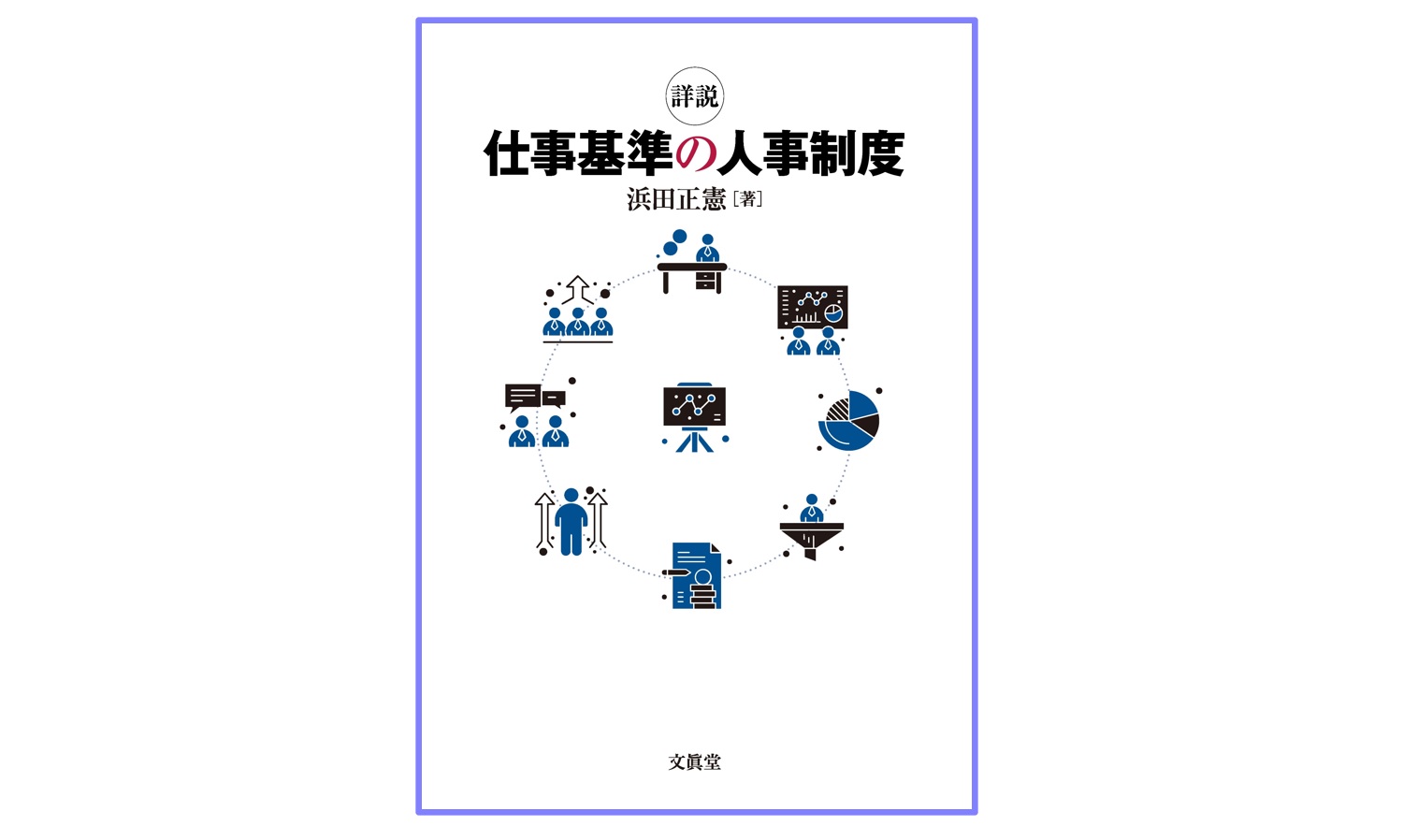News
最新情報
- 2026/02/18
- セミナー・出版中堅企業の人事戦略 (2026/3/18 開催 無料セミナー)
- 中堅企業の経営者、人事担当者の方が人事戦略やジョブ型人事制度のひとつ「役割等級制度」の理解を深め、人事機能で組織改革を進めるためのヒントを見つけていただくためのセミナーです。 この様な課題を意識されている方は、ぜひご受講下さい!
詳細はこちら
- 2025/07/21
- セミナー・出版「早稲田学報」で「詳説 仕事基準の人事制度」をご紹介いただきました。
- 「早稲田学報(2025年8月号)」で、「詳説 仕事基準の人事制度」をご紹介いただきました。 詳細はこちら
- 2025/03/31
- お知らせオフィス移転のお知らせ
- 弊社オフィスは、渋谷区に移転しました
詳細はこちら
- 2024/11/15
- セミナー・出版「月刊 社労士」で「詳説 仕事基準の人事制度」をご紹介いただきました。
- 全国社会保険労務士会連合会が発行する「月刊 社労士」で、「詳説 仕事基準の人事制度」をご紹介いただきました。 詳細はこちら
- 2024/09/28
- セミナー・出版「日本の人事部」で「詳説 仕事基準の人事制度」をご紹介いただきました。
- 日本最大級の人事向けポータルサイト「日本の人事部」で「詳説 仕事基準の人事制度」を取り上げていただきました。 詳細はこちら
Features
私たちの特徴
コンピテンシーコンサルティングは、組織・人事領域を専門とする経営コンサルティングファームです。
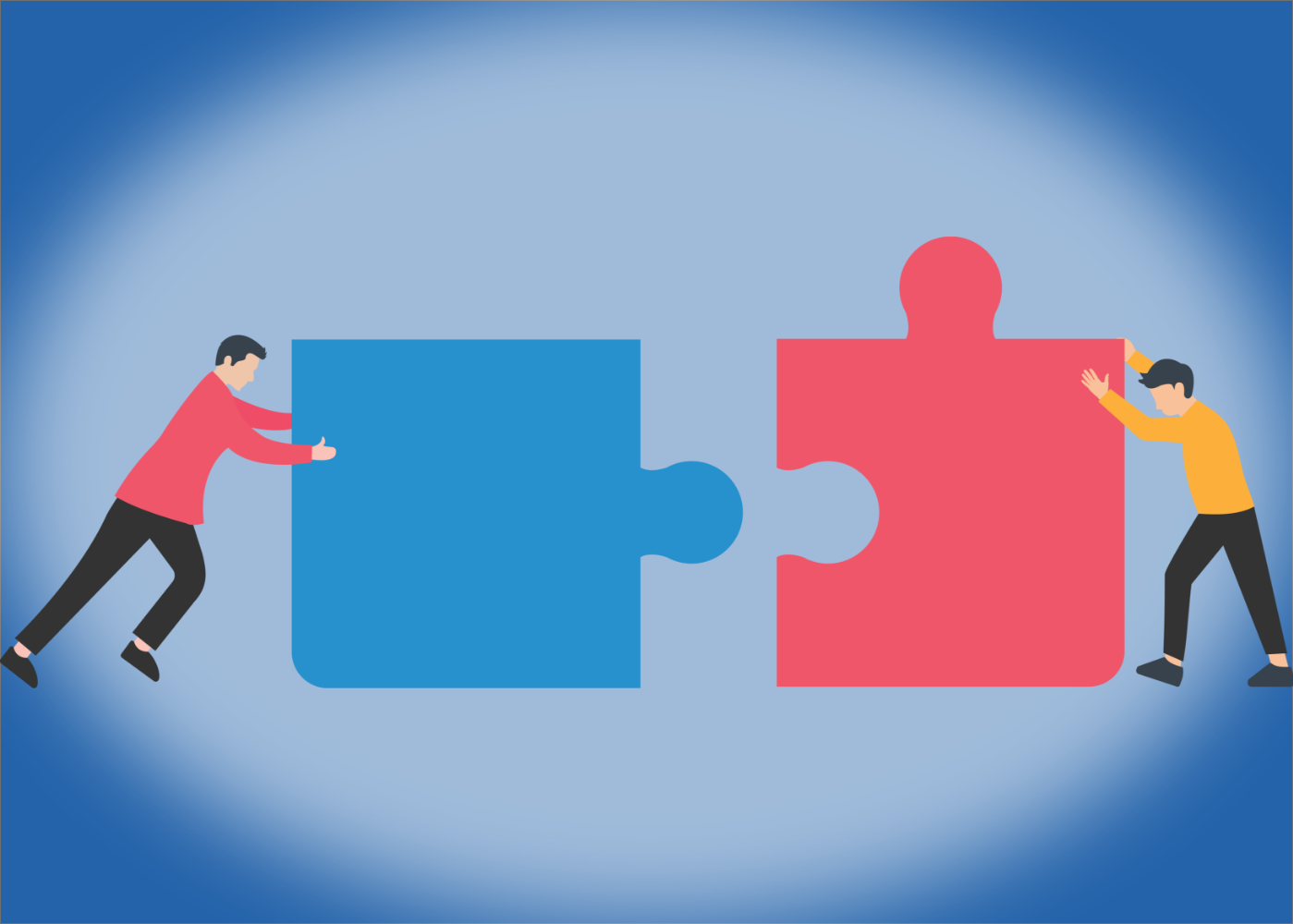
人事の仕組みと経営戦略を
一致させます
弊社は、経営者と一緒に経営目標の達成のために「人事の仕組みをどのように活用すればいいか」を考えます。単なる人事機能の改善だけではなく、貴社の経営戦略の実現を支援し、業績向上につながるコンサルティングを行います。
経営理念・ビジョンを実現するための方向性を整理し、バランススコアカードを用いて貴社の経営戦略の中に具体的な人事施策を埋め込みます。コンサルティングに「コンピテンシー」を活用いたします。「コンピテンシー」を「高業績者の行動特性」と捉え、経営改善に結びつく行動を定義します。その行動を実践し、成果を出す社員を育成する人事施策を構築します。

人事制度を定着に導きます
弊社のコンサルティングは、人事制度の構築や見直しで終わるのでなく、導入とその後の運用まで一貫して支援いたします。
人事制度の定着の鍵を握る関係者(役員や管理職など)への合意形成を図りながらコンサルティングを行います。弊社のコンサルタントが人事部門の方々と一緒になって、役員会や社員説明会に参加し、関係者への説明を行います。制度の定着のための研修を人事部門と協力しながら実施いたします。また、人事制度の運用のノウハウをしっかり移管するよう努めます。

豊富な経験と知識を持った
専門家によるコンサルティング
コンピテンシーコンサルティングのコンサルタントは、コンサルティングファームや民間企業で長年の経験を積んできました。特に、人事分野における豊富な経験を持っており、貴社のニーズや課題を深いレベルで共有し、具体的な解決策をご提案いたします。
弊社のコンサルタントはMBAや社会保険労務士などの専門資格を有しており、専門的な知識を活かしたコンサルティングを行います。特に、労働法や就業規則の設計・運用に精通しており、法的なリスクを抑えながらスムーズに制度設計・導入を進めます。
Services
サービス
コンピテンシーコンサルティングは、
組織・人事領域を専門とする経営コンサルティングファームとして、
企業が抱える経営課題を解決します。
サービス一覧ページよりご覧いただけます。

Problem
Solving
課題解決
自社の現状とあるべき姿の理解を促し、経営課題を明確にします。

ジョブ型人事制度を
取り入れたい
等級定義書、評価シート、昇給ロジックなどの設計だけでなく、2つの大前提に対応するために、組織構造の見直し、社員の再格付け、社員の給与の移行など、難しい導入部分でもしっかり支援をいたします。
管理職を
しっかり育てたい
以下のような管理職研修でお客様のニーズに応えています。どの研修も、企業固有のビジネス・人事制度・組織課題に応えるため、コンテンツをカスタマイズし、お客様単位で実施しております。
Information
最新情報
用語集
用語集はこちらから。